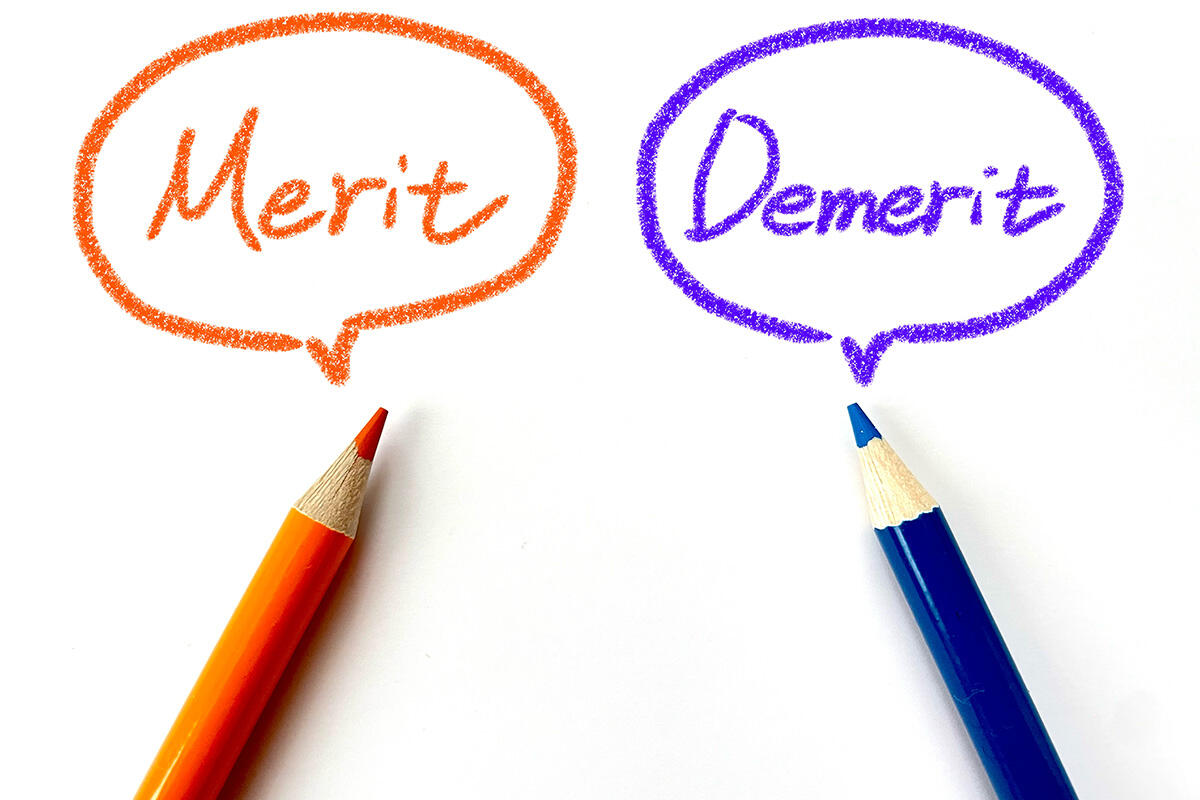フリーランスエンジニアを活用するには?~社会保険料引き上げにおける影響~
昨今の法改正や制度改定などに伴い、企業は経費削減や労働力の最適化を求められる状況に直面しています。2025年1月、厚生労働省は厚生年金保険料の上限を2027年9月から段階的に引き上げる方針を示しており、これにより高所得の従業員とその事業主の保険料負担が増加することが予想されます。
本コラムでは、公的年金制度の仕組み、企業や社員への影響、企業が講ずべき対策について、業務委託やフリーランスの活用が有効な手段である理由を探ります。

目次
公的年金制度のおさらい
国民年金と厚生年金
日本の年金制度は、すべての国民が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社員・公務員などが加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。
国民年金と厚生年金は加入者、保険料、年金額、受給条件において異なります。
厚生年金を算出する指標としては、標準報酬月額※、標準賞与額、被保険者期間、年齢、保険料率などを基に厚生年金の保険料や将来の年金受給額が計算されます。
標準報酬月額の上限改定の2つの重要な目的は、収入に応じた負担(応能負担)の強化と、所得再分配機能の強化です。この標準報酬月額の上限引き上げによって保険料収入が増加することで、将来世代の年金受給水準全体を改善する効果が期待されています。
| 年金の種類 | 対象加入者 | |
|---|---|---|
| 国民年金(基礎年金) | 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての国民 | 国民共通の土台部分 フリーランスや自営業者・学生、専業主婦(主夫)など |
| 厚生年金 | 会社員・公務員など(加入条件に当てはまる従業員) | 国民年金に上乗せ(報酬比例年金) 毎月の掛け金は雇用されている企業と従業員で折半 |
- 標準報酬月額とは、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区分したもの。
出典:日本年金機構 厚生年金保険料額表
2027年9月〜|標準報酬月額の上限が改定予定
2025年1月、厚生労働省が、2027年9月〜2029年9月にかけて、標準報酬月額の上限を3段階で引き上げる方針を示しました。
想定されている具体的な引き上げのスケジュール
- 2027年9月:65万円→68万円(第33級新設)
- 2028年9月:68万円→71万円(第34級新設)
- 2029年9月:71万円→75万円(第35級新設)
厚生年金引き上げの具体例や影響
保険料負担増加の具体例
厚生年金保険料の引き上げは、事業主にとっても大きな負担となります。以下に、事業主の保険料負担増加の具体例を示します。厚生年金保険料は、従業員の標準報酬月額に基づいて計算され、従業員と事業主が半分ずつ負担します。
- 標準報酬月額: 従業員の給与や手当を基に計算される月額報酬
- 保険料率: 厚生年金保険料率は法律で定められており、2023年10月時点で18.3%
従業員1人当たりの社会保険料負担の計算・従業員100人の場合の企業負担額
企業全体の負担増加額は、対象となる従業員数によって大きく変わります。例えば、対象従業員が100人いる企業では、最終的に月額90万円(年額1,100万円程度)の負担増となる計算です。高給与の従業員が多い企業では、この負担増が経営に大きな影響を与える可能性があります。
| 現在 | 2027年9月 | 2028年9月 | 2029年9月 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準報酬月額 | 65万円 | 68万円へ引き上げ | 71万円へ引き上げ | 75万円へ引き上げ |
| 保険料率 | 18.3%(従業員負担分:18.3% ÷ 2 = 9.15%) | |||
| 従業員の月額負担 | 65万円 × 9.15% = 59,475円 | 68万円 × 9.15% = 62,220円 | 71万円 × 9.15% = 64,965円 | 75万円 × 9.15% = 68,625円 |
| 企業の月額負担(従業員1人当たり) | 65万円 × 9.15% = 59,475円 | 68万円 × 9.15% = 62,220円 | 71万円 × 9.15% = 64,965円 | 75万円 × 9.15% = 68,625円 |
| 企業の月額負担総額(従業員100人の場合) | 59,475円 × 100人 = 5,947,500円 | 62,220円 × 100人 = 6,222,000円 | 64,965円 × 100人 = 6,496,500円 | 68,625円 × 100人 = 6,862,500円 |
厚生年金引き上げによる企業と従業員への影響
企業において
- 経費負担の増加
- 企業が負担する厚生年金保険料が増加することで、経費が増え、利益率が低下する可能性があります。他、企業年金や社会保険給付などにも影響を与えます。
- 雇用・人事戦略の見直しの必要性
- 高所得の従業員に対する保険料負担が増えることで、採用計画や人材確保の難易度が高くなる可能性があります。
- バックオフィス負担の増加
- 実務面での負担として、システム改修や従業員への説明、就業規則や給与規定などの改定が必要になるケースもあります。
従業員(高所得者)において
- モチベーションの低下
- 手取り収入の減少:生活水準や消費活動に影響を与え、結果モチベーションが低下する可能性があります。
- 給与の相対的価値の低下:同じ給与額でも手取りが少なくなり、自身の労働に対する対価が減少したと感じる可能性があります。
- 離職リスクの増加
- 競合他社への流出:高所得者層は、スキルや経験が豊富であるため、他の企業からの引き合いが多いこともあります。保険料負担の増加に不満を感じた従業員が、より良い条件を提示する競合他社に転職するリスクが高まります。他社が同じ給与水準でも、福利厚生やフレキシブルなはたらき方を提供している場合、高所得者層は魅力を感じて転職を考える可能性があります。
- フリーランスへの転向:高所得者層は、自身のスキルや専門知識を活かしてフリーランスとしてはたらくことも選択肢となります。
雇用の流動化
雇用の流動化と解雇規制
日本の労働市場においては、労働者の雇用に関する権利が強く保護されています。特に、日本の解雇規制は厳しく、容易に従業員を解雇することができないため、企業においては、保険料の折半負担や固定費の増加といったコスト面の課題が重くのしかかるなど人件費の圧迫を受けやすく、持続可能な経営が困難になることがあります。 そのため雇用の流動化を進めることで、経済的な柔軟性を高め、生産性の向上やコスト削減を実現することができます。
解雇規制が厳しい中で雇用の流動化を促進する際には、解雇時の対応や採用・評価基準の見直し、即戦力採用の一般化などを検討することが重要です。このような流動化の促進は労働市場の活性化を高め、社会的な経済成長にもつながっていきます。
また、企業には従業員の雇用においても考慮すべき項目がいくつかあり、多方面からの注意も必要です。ポイントをしっかり押さえ、「柔軟な人材活用」を進めることで、企業は競争力を高め、持続可能な成長を目指すことができます。そのためには、これまでのメンバーシップ雇用から、フリーランスなどのジョブ型雇用への移行などの検討を行うことが重要な要素の一つとなります。
解雇規制における、雇用の流動化の考慮すべき注意点
- 法的コンプライアンスの厳守
不当解雇や契約違反にならないよう労働基準法やその他の関連法規など、労働法の厳守 - 適切な契約の締結
業務内容、報酬、期間、成果物の納品条件などを明確に記載した契約書を締結 - コミュニケーションの強化
フィードバックや進捗確認など、定期的なコミュニケーションの実施 - 公平な評価と報酬
適切な評価と報酬、公平な評価制度の設定 - 知的財産権の管理
創出した知的財産についての条項など権利関係を明確化 - セキュリティ対策
機密情報の取り扱いやデータの保護に関するガイドラインなど、適切なセキュリティ対策の実施 - 労働環境の整備
フレックスタイムやリモートワークなど、柔軟なはたらき方の提供 - 継続的なスキルアップ支援
必要なスキルや知識を習得するための教育や研修の提供
企業の対応策
1.増加し続ける保険料負担に対して、企業が講ずべき対応策とは
企業は、保険料負担の増加に対し、業務の最適化やコスト管理、柔軟なはたらき方の導入などの対策を講じることが重要です。また従業員のスキルアップや健康管理を支援することで、従業員の生産性と満足度を向上させ、結果的に企業全体の競争力を高めることにつながります。これにより、企業は保険料負担の増加を乗り越え、持続的な成長を実現することができます。
企業向け
| 業務委託やフリーランスの活用 | 固定的な社会保険料負担を軽減し、必要なスキルを柔軟に確保することができます。 |
|---|---|
| 労働力の最適化 | 社員の配置転換や業務のアウトソーシングなどを検討し、労働力を最適化することで、効率的な経営を実現します。 |
| フレキシブルな報酬パッケージの提供 | 給与の一部を福利厚生やパフォーマンスボーナスに置き換えることで、従業員の満足度を維持しながら保険料負担を軽減することができます。(例: 健康保険、住宅手当、教育・研修プログラムなど福利厚生の拡充) |
| 給与体系の見直し | 賞与やインセンティブを強化し、基本給を抑えることで、保険料の基礎となる報酬総額を調整します。 |
従業員向け
| キャリア開発と成長機会の提供 | 従業員のスキルアップを支援することで、生産性を向上させ、企業の競争力を高めます。これにより、企業全体の収益が向上し、保険料負担の増加にも対応しやすくなります。 |
|---|---|
| 柔軟なはたらき方の導入 | テレワークやフレックスタイム制など、柔軟なはたらき方を導入することで、従業員のワークライフバランスを向上させ、はたらきやすい環境を提供します。 |
| 健康管理支援、メンタルヘルスサポート | 健康管理を支援することで、病気やケガによる欠勤を減少させ、結果的に生産性向上につなげます。またメンタルヘルスに関するサポート体制を整え、従業員の精神的な健康を維持することで、ストレスやバーンアウトを防ぎます。 |
| コミュニケーションの強化 | 定期的な面談やフィードバックを通じて、従業員とのコミュニケーションを強化し、はたらきやすい職場環境を築きます。 |
2.「業務委託やフリーランスの活用」を検討する際のコストメリット
フリーランスの活用は、企業にとって保険料負担の軽減だけでなく、コストの変動費化、専門スキルの活用、柔軟なリソース調整、採用・育成コストの削減、経営の迅速化など多くのメリットをもたらします。これにより、経済的な負担を減らしつつ、競争力を高めることができます。
「業務委託やフリーランスの活用」を検討する際のコストメリット
- 厚生年金保険料や社会保険料の削減
企業側での社会保険料や厚生年金保険料を負担する必要がありません。これにより、企業の保険料負担が大幅に軽減されます。 - コストの変動費化(固定費の削減)
正社員の雇用に比べて、業務委託やフリーランスはプロジェクトベースでの契約が可能であり、人件費を変動費として扱うことができます。これは、経費の柔軟な管理を可能にします。 - 専門スキルの活用(高い専門性の確保)
フリーランスエンジニアや業務委託者は特定の専門スキルを持っていることが多く、短期間で高度な業務を遂行することが可能です。これにより、プロジェクトの質と効率が向上します。 - 柔軟なリソース調整
業務の繁閑に応じて、必要な時に必要なだけのリソースを確保できます。これにより、過剰な人員を抱えるリスクを軽減できます。 - 採用・育成コストの削減
フリーランスエンジニアや業務委託者は即戦力として活用できるため、新規採用や社員教育にかかるコストを削減できます。 - 経営の迅速化(迅速なプロジェクト遂行)
専門スキルを持つフリーランスエンジニアを活用することで、プロジェクトの立ち上げから完了までの期間が短縮され、迅速な対応が可能になります。
まとめ: フリーランスエンジニア活用におけるコストメリット
昨今の法改正や制度改定などに伴い、企業は経費削減や労働力の最適化を求められる状況に直面しています。会社経営の維持には、さまざまな課題がありますが、保険料などのコスト面の課題においては雇用の流動化を進めることで、経済的な柔軟性を高め、生産性の向上やコスト削減を実現することができます。
企業は増加し続ける保険料に対し講ずべき対策や注意点などに留意しつつ、フリーランスの活用によるコスト削減や労働力の最適化を実現し、経営の迅速化や専門スキルの活用といった多くのメリットを享受することができます。これにより、変動する経済環境に適応し、持続可能な成長を目指すことが可能となります。