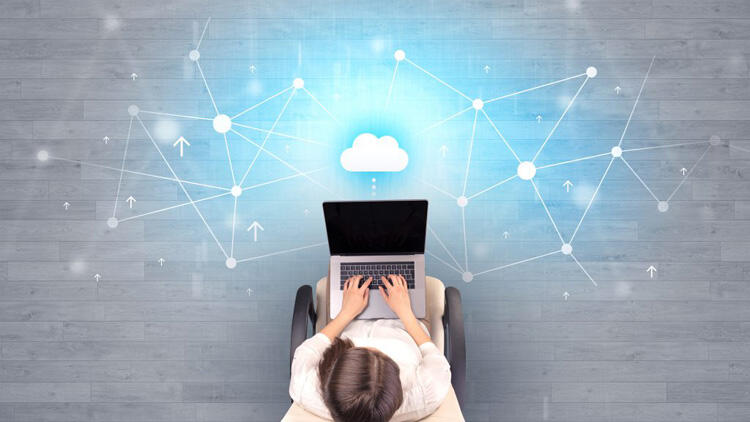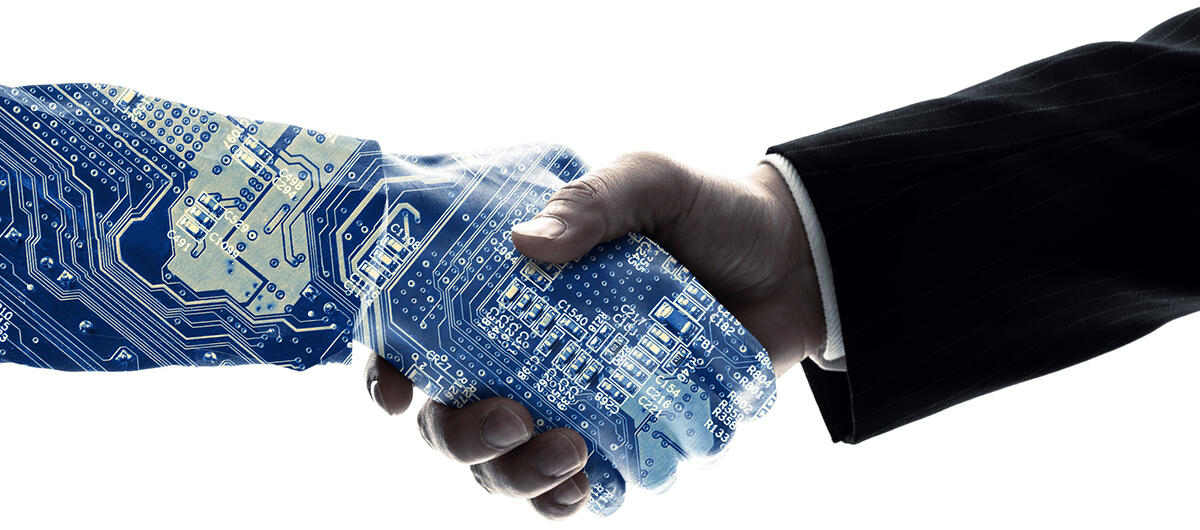VDI(仮想デスクトップ)を初心者にもわかりやすく解説!仕組みやメリット・デメリット、リモートデスクトップとの違い
リモートワークが普及している今、多くの企業でVDI(仮想デスクトップ)の導入が検討されています。しかし、仕組みがよくわからないという声も少なくありません。また、導入にあたってセキュリティ面の安全性を気にしている方も多いでしょう。
この記事では、VDI(仮想デスクトップ)の基本的な仕組みから、導入によって実現できるはたらき方、セキュリティやコスト面でのメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。この記事を参考に、VDIの導入を検討してみましょう。

目次
パーソルクロステクノロジーの Azure Virtual Desktop導入支援サービスは、Azure Virtual DesktopやVDIの導入をご支援いたします。
VDIを利用したセキュアなリモートワーク環境の構築について課題をお持ちのお客さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら
VDI(仮想デスクトップ)とは?
まずは、VDI(仮想デスクトップ)という言葉の意味や仕組みを解説します。
VDIの定義
VDI(Virtual Desktop Infrastructure:仮想デスクトップ)は、従来パソコンにインストールしていたOSやアプリといったデスクトップ環境をサーバー上で仮想的に構築し、ユーザーがネットワーク経由でアクセスできるようにする技術です。業務で利用しているパソコンが手元になくても、インターネットに接続できる端末さえあれば、まるで手元にパソコンがあるかのように作業を進められます。
VDIの仕組み
VDIでは、業務で使用するOS、ミドルウェア、各種アプリなどがすべてサーバー側に用意されています。ユーザーがキーボードやマウスで操作をおこなうと、その指示がネットワークを通じてサーバーに送信され、サーバー側でプログラムが実行される仕組みです。
処理された画面データや音声データは、リアルタイムでユーザーの端末に送り返されるため、あたかも手元の端末でアプリが動作しているような感覚で利用できます。
また、この仕組みにより、端末側で処理の重いアプリを直接実行する必要がなくなり、高度な処理機能を持たない端末でも高性能なアプリを利用することが可能となります。
VDI(仮想デスクトップ)の3つの種類
VDIはサーバーの配置方法によって大きく3つの種類に分かれます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
| 項目 | オンプレミス型 | クラウド型 | ハイブリッド型 |
|---|---|---|---|
| サーバー | 自社内の物理サーバー | サービス事業者のクラウドサーバー | 自社内+クラウドサーバー |
| 初期コスト | 高額 | 低額 | 中程度 |
| 運用コスト | 自社のリソースに依存 | 継続的なサービス利用料 | 中程度 |
| メンテナンス | 自社内で対応 | サービス事業者が対応 | 自社内は自社、クラウドはサービス事業者が対応 |
| カスタマイズ性 | 高い | サービス事業者によって制限あり | 中程度 |
オンプレミス型
オンプレミス型は、企業が自社で保有するサーバー上にVDI環境を構築する方式です。物理サーバーを自社で保有するために初期コストが高額になりやすく、運用も自社内で完結させる必要があります。自社内に管理運用できる技術者がいない場合は、運用委託などの運用コストが高額になる可能性もあります。
一方、システム全体を自社で管理するため、セキュリティポリシーや業務要件に合わせた細かなカスタマイズが可能です。導入から運用・保守までを自社の裁量で進められるため、既存システムとの連携や独自の機能追加なども比較的容易におこなえます。
費用や管理負担は大きいものの、導入から保守まで柔軟性が高いのが、オンプレミス型の特徴です。
クラウド型
クラウド型は、AWSやMicrosoft Azureなどのクラウドサービス上で事業者が提供するVDIサービスを利用する方式です。自社で物理サーバーを用意する必要がないため、初期投資や導入までのリードタイムを大幅に抑えられます。
運用面においても、利用数に応じて柔軟にリソースと費用を調整できる点がメリットです。しかし、利用期間中は継続的にサービス料金が発生するため、長期的な運用コストを考慮して利用を検討しましょう。
メンテナンス面では、システムの保守・管理は事業者側が担当するため、自社のIT部門の負担を軽減できます。一方で、事業者が提供する標準的なサービス範囲内での利用となるため、細かなカスタマイズには制約があります。また、サービスの可用性やサポートの充実度も事業者に依存するため、どのサービスを利用するかは慎重な検討が必要です。
ハイブリッド型
ハイブリッド型は、オンプレミス型とクラウド型を組み合わせて構築する方式です。例えば、機密性の高い業務はオンプレミス環境で処理し、一般的な事務作業はクラウド環境を活用するといった使い分けをします。
ユーザーの役割や業務内容に応じて最適なVDI環境を提供できるため、コストとセキュリティのバランスを取りながら運用可能です。ただし、複数の環境を管理する必要があり、運用の複雑さが増す傾向にあります。
VDI(仮想デスクトップ)のメリット

VDI導入には企業に多くのメリットをもたらします。代表的なメリットを4つご紹介します。
システム運用管理の効率化
従来のパソコン環境では、端末ごとにソフトウェアをインストールし、設定やアップデート適用をおこなう必要がありました。一方、VDIは設定変更やメンテナンス作業をサーバー側で一括しておこなえるため、作業時間を大幅に短縮できます。
例えば、100台の端末のアプリをアップデートする場合、従来だと各端末にパッチを配信していました。しかしVDI環境では、サーバー上のアプリをアップデートするだけで全ユーザーに反映されます。このような運用効率化により、システム管理者の作業負担が軽減され、IT部門のリソースをより戦略的な業務に集中させることができます。
多様なはたらき方の実現
VDIでは業務に必要なOSやアプリがサーバー上に配置されているため、自宅のパソコン、外出先のタブレット、顧客からの貸与パソコンなど、インターネット接続可能な端末であればどこからでも同じ作業環境にアクセスできます。
プログラムの処理もサーバー上でおこなわれるため、端末に高いスペックは求められません。テレワークやサテライトオフィスといった多様なはたらき方を実現でき、従業員のワークライフバランス向上と生産性向上が両立可能です。
セキュリティ強化
VDIはサーバー側で操作や処理を実行する仕組みになっているため、端末側にはデータが保存されません。そのため、VDIにアクセスする端末で紛失や盗難が発生してもデータの漏えいを防ぐことができます。また、ユーザーの操作ログを一元的に記録・監視できるため、内部不正の早期発見にもつながります。
BCP(事業継続計画)強化
VDIはBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対応の一環としても活用されています。自然災害やサイバー攻撃などによってオフィスの端末が利用できなくなったとしても、サーバーが無事であれば、別の端末・場所から業務を継続できるためです。
クラウド型VDIを選択した場合は、地理的に離れた複数のデータセンターを使ってVDI環境を構築することで、より災害に強い業務環境を構築することもできます。コロナ禍のような突発的な環境変化にも柔軟に対応できるでしょう。
VDI(仮想デスクトップ)のデメリット
VDIには多くのメリットがある一方、導入前に把握しておくべき課題もあります。VDIの主な注意点を見ていきましょう。
導入・運用コストがかかる
VDIの導入と運用には多額のコストがかかります。特にオンプレミス型を選択した場合、高性能な物理サーバーや専用のストレージ、ネットワーク機器などを自前で調達する必要があり、初期コストが非常に高額になります。
導入後も、システムの監視やアップデート、定期的なハードウェア更新、ストレージ増設などで継続的な運用費がかかります。自社内に十分な技術者がいない場合は外部の支援を受けることで運用負担の軽減と品質向上が図れますが、これらのサービス利用にも別途費用が発生するため、トータルでのコスト計算が欠かせません。
ネットワークやサーバーに依存する
VDIの快適性は、ネットワーク環境とサーバー性能に大きく左右されます。サーバー側で接続数や処理内容に対するキャパシティが不足すると、ユーザーの処理が重くなり、作業効率の低下につながります。
また、VDIは端末側の環境に依存しにくい技術ではありますが、従業員の家庭のネットワーク環境によっては、Web会議での音声や映像などに遅延が発生する可能性があります。テレワークでの導入を前提とする場合は、モバイルWi-Fiの提供など、通信環境のサポートも考慮しておくとよいでしょう。
サーバー障害の影響範囲が大きい
仕組み上、VDIのサーバーやネットワークで障害が発生すると、そのサーバーを利用するすべてのユーザーが同時に業務を停止せざるを得なくなります。一度の障害による影響が大きくなるため、リスクを最小限に抑える取り組みが重要です。冗長化された(性能やデータの同じスペアが準備された)サーバー・ネットワーク構成の採用や、バックアップ取得などを検討しましょう。
また、クラウド型VDIを選択する場合は、事業者のサービスレベル契約(SLA)や障害対応体制が充実した、信頼性の高い事業者を選ぶようにしましょう。
「Azure Virtual Desktop導入支援サービス」とは?
VDIは多くのメリットが得られる技術ですが、構築・運用にかかる専門性が高く、うまく活用できていない企業が多いのも実情です。専門性やノウハウに不安がある場合には、導入支援サービスの活用を検討するとよいでしょう。
パーソルクロステクノロジーでは、Microsoft Advenced Specialization認定パートナーとして、高い専門性とノウハウをもとにVDI導入を支援するサービスをご提供しています。運用設計やサイジング、セキュリティ対策など、お客さまの環境に合わせたサービスをご提供しています。VDIの導入をご検討中のお客さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
サービス:Azure Virtual Desktop導入支援サービス
VDI(仮想デスクトップ)の導入事例
ある大手金融機関さまでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、急遽リモートワークを実現できる環境を整備する必要に迫られていました。本番環境のリリースまで3週間と非常に短い期間で構築を進めなければならない一方、金融機関という特性上、セキュリティにも十分な配慮が求められる状況でした。
そこで、短期間で強固なセキュリティを持つVDI環境を構築するために、Microsoft純正のクラウドVDIサービスを採用。パーソルクロステクノロジーの支援のもと、同時アクセス800名のリモートワーク環境を実現しています。結果として、コロナ禍においても業務を継続できる環境の迅速な構築に成功しました。
事例:本番リリースまで1ヵ月未満、コロナ禍において求められるセキュアなリモートワーク環境の構築(大手金融機関 様)
リモートデスクトップやシンクライアントとの違い
VDIと混同されやすい技術として、リモートデスクトップとシンクライアントがあります。VDI導入前に、これらの技術との違いを理解しておきましょう。
リモートデスクトップとの違い
リモートデスクトップとは、特定の物理的なパソコンにネットワーク経由でリモートアクセスする技術です。基本的に「1対1」での接続であり、同時に接続できるユーザーは1人だけです。
一方、VDIは、リモートデスクトップとデスクトップ環境の仮想化を組み合わせて「1対n」の接続と操作を可能にした技術です。複数の接続や処理を一元的に管理できるため、物理的な機器数の削減に加え、メンテナンスやセキュリティ対策がしやすいというメリットがあります。
| 項目 | リモートデスクトップ | VDI |
|---|---|---|
| アクセス先 | 物理的なパソコン | サーバー上の仮想環境 |
| 同時接続数 | 1対1 | 1対n |
| メンテナンス・セキュリティ対策 | 個別管理 | 一元管理 |
| 可用性 | 低 | 高 |
| 導入コスト | 高 | 低 |
シンクライアントとの違い
シンクライアントは、ユーザーが操作する端末側では最小限の処理のみをおこない、実際のアプリ実行やデータ処理はサーバー側でおこなう方式の総称です。VDIはシンクライアントの方式の一種といえます。
シンクライアントには、VDIのような仮想環境の画面のみを転送する画面転送型の他にも、ネットワーク経由でOSイメージを端末にダウンロードして利用するネットブート型などがあります。
VDI(仮想デスクトップ)を生産性向上やBCP強化に役立てよう
VDIは、従来のパソコン環境をサーバー上で仮想化し、ネットワーク経由でアクセスできる技術です。オンプレミス型、クラウド型、ハイブリッド型の3つの導入形態があり、初期コストやカスタマイズ性などが大きく異なります。
VDIの導入には、業務効率化やはたらき方の多様化の実現、セキュリティ強化、BCP対応強化などのメリットがある一方、導入・運用コストの高さ、ネットワークやサーバーへの依存性、サーバー障害時の影響範囲の大きさというデメリットも存在します。
デメリットを抑えてメリットを最大化するためには、外部の専門的なリソースを活用することがおすすめです。パーソルクロステクノロジーでは、クラウドを活用したVDI構築支援サービスをご提供しています。VDI環境の構築にご興味をお持ちの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
サービス:Azure Virtual Desktop導入支援サービス
- ※本コラムに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。