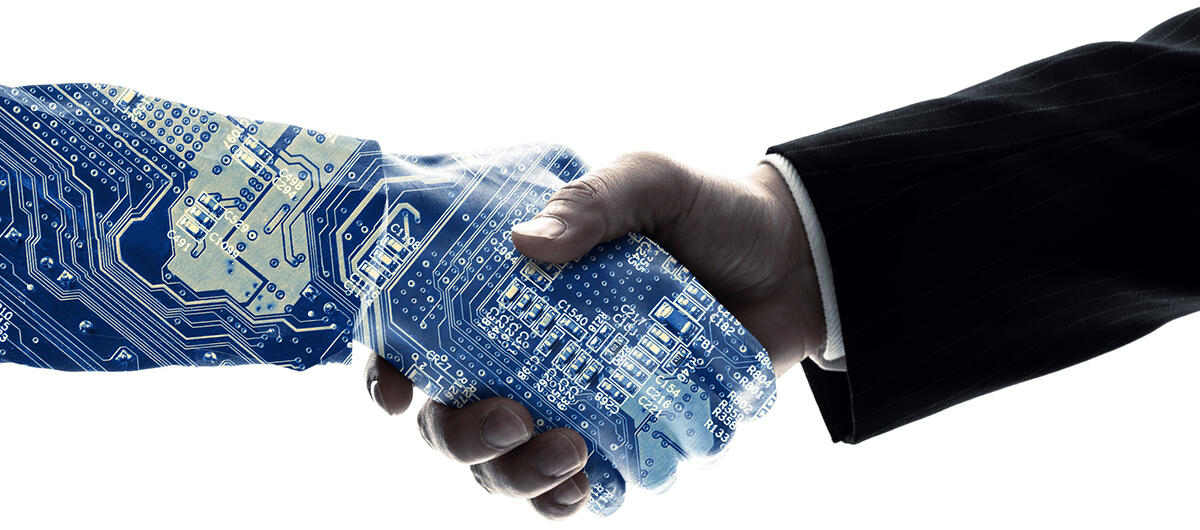製造業DXとは? デジタル化の課題や進め方、事例を紹介
製造業におけるDXは、業界内での生き残りを左右するほどの重要な取り組みです。しかし、具体的にどう取り組めばよいのか、その明確なイメージを持つことが難しい用語でもあります。
この記事では、製造業DXの意味や必要性、実現できること、導入の流れや課題、事例、便利な支援サービスなどについてご紹介します。

目次
パーソルクロステクノロジーではデジタル / リアル、製造 / 物流を総合的に考慮した製造業DX構想策定支援を提供しています。自社のDX推進を成功させたいお客さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら
製造業DXとは?
製造業DXとは、AIやIoTなどのデジタル技術を用いて製造業者が自社のビジネスモデルを大きく変革させる取り組みを指します。
もともとDXとは、デジタル技術の活用により自社の事業を抜本的に改革していく取り組みのことです。作業のデジタル化(例:紙の書類をパソコン入力に変更)を意味するデジタイゼーションや、業務のデジタル化(例:勤怠管理をITツール管理に統一)を意味するデジタライゼーションといった言葉のさらに先にある概念となります。
製造業DXの特徴は、ある作業をデジタル化するといった単純な改善を超え、より劇的な生産性の向上を目指す点にあります。例えば、AIによる需要予測から最適な生産計画を導きだし、自動化されたラインがそれを受けて24時間稼働するなど、製造の常識さえ変わるような施策を意味します。
製造業DXの市場規模
株式会社矢野経済研究所の調査によれば、国内の工場デジタル化[現場向けIT投資、IoT・クラウド・AIといったITテクノロジーの適用、データ基盤の構築(スマート工場/デジタル工場化)などを目指した取り組み]に関する市場規模は、2025年度で1兆9,180億円と予測されています。2030年度にはさらに2兆1,800億円にまで成長すると予測されており、製造業DXが実現しつつある状況が報告されています。
出典:(株)矢野経済研究所「工場デジタル化市場に関する調査(2025年)」(2025年4月30日発表)
- ハードウェア、ソフトウェア、プラットフォーム(クラウド)利用料、工事費(電気設備・通信設備)、SI・コンサルティング、サービス・サポート費、保守メンテナンス、要員派遣などを対象として、ユーザー企業のITベンダーなどへの発注金額ベースで算出した。
製造業DXが進まないとされる背景
一方で、製造業DXが思うように進まない現状もあります。その背景には、以下のような理由があります。
- 必要な予算を確保できない
- 現場の理解を得るのが難しい(自分の仕事を奪われるのではと懸念されやすい)
- 部門間の連携がうまく進まない
- 業界知識とITの知見を併せ持つ自社人材がいない
- 製造業界ならではのアナログ文化が根強い(例:紙の書類を好む取引先など)
- 自社がおこなうべき改革が何か判断できない
- そもそも製造業DXのイメージがつかめていない など
一部の大企業が積極的に製造業DXを進めるなか、なかなか変革が進まない事業者もいるのが実状です。自社での対応が困難な場合は外部サービスを利用するなどの対策が必要になることもあるでしょう。
製造業DXの必要性
製造業DXは、製造にまつわる人や組織の生産性の向上を目的としています。こうした取り組みが必要される背景には以下のような理由があります。
競争力の強化
消費者ニーズの多様化や国内市場の成熟、安価な海外製品の広がりなどにより、他社に負けない競争力の確保は、多くの製造業者にとって喫緊の課題です。価格や品質のみを武器とするのは難しく、DXによる開発速度や顧客・取引先対応の品質の向上など、総合的なレベルアップの必要性が増しています。
経営リスクの多様化
関税問題、パンデミック、異常気象や戦争など、近年は製造業にも少なからず影響を及ぼす経営リスクが増えています。サプライチェーンの混乱や原材料費・エネルギーコストの高騰など、起こりうる問題はさまざまです。そうした問題において、DXにより意思決定の速度を改善することは重要なリスクヘッジとして機能します。
既存ITシステムの限界
「2025年の崖」として語られてきたように、日本の製造業で利用されている既存ITシステムは限界を迎えつつあります。老朽化や複雑化が進むなか、運用コストはかさみ続けており、新製品の開発や新たな機材の導入といった前向きな取り組みに割くべき予算を圧迫しています。DXにより最新のITツールを導入することは、それ自体がランニングコストの削減策として有効です。
人材不足と高齢化
少子高齢化による労働人口の減少が指摘されるなか、さまざまな業界で人材不足が叫ばれています。日本の基幹産業である製造業も例外ではなく、技術を持ったベテランの引退や後継者となる若手の不足が問題視されています。DXによる作業の自動化や省人化がその解決策として期待されています。
製造業DXで実現できること
では、製造業DXによって具体的に何が実現できるのでしょうか。
生産現場の自動化
生産現場の各工程の自動化は、製造業DXの代表的な取り組みです。IoTや産業ネットワークの進化もあり、最近では多様な作業を機械に任せられるようになりました。
例えば、カメラにより通路の障害物を回避しながら原材料を運べるロボットが登場するなど、臨機応変な対応も可能になりつつあります。
在庫管理の効率化
製造業DXでは、WMS(倉庫管理システム)というシステムの導入により在庫管理の効率化が実現できます。倉庫への入荷から出荷までをシステマチックに管理でき、棚卸し誤差や在庫ロスを削減しやすくなります。
WMSの詳細は以下の記事も併せてご覧ください。
WMS(倉庫管理システム)とは?機能や導入メリット、選び方について
品質管理の高度化
デジタル技術による効率的な不良品の検知も、製造業DXで実現できることの1つです。カメラ映像をAIが画像認識により解析して異常のある製品を見つけ出すなどの仕組みが登場しています。
担当者による管理のムラをなくし、品質のばらつきを最小限に抑えられます。
保守効率の改善
製造業DXでは、IoTのデータ収集とAIによる将来予測により、設備の故障リスクを予測する取り組みも進んでいます。
従来は壊れてから修理するのが当たり前でしたが、故障を未然に察知し対応することが可能となり、メンテナンス費用の低下やライン稼働率の向上につながっています。
経営判断力の強化
製造業DXを進める過程では、工場内外のデータを収集・一元管理して活用策を検討します。
これによりデータを根拠にした建設的な議論が可能となり、担当者の主観に頼っていた頃と比べて経営判断の速度や精度が向上します。
競争優位性の強化
ここまでご紹介した5つの改善により、自社の競争力は強化されます。
ほかにも、データをもとにした市場分析と需要予測、受発注管理や労務管理の自動化、先進的な企業としての人材確保の優位性の向上など、実現できる恩恵は数多くあります。
製造業DX導入の流れ
製造業DXを導入するまでの一般的な流れは、大きく7つのステップからなります。
現状把握と課題の特定
最初の作業は、現状把握とDXで解決すべき課題の特定です。現場へのヒアリングや手元にあるデータの分析を通じて自社が抱えている非効率を炙り出しましょう。
以下は発見されやすい課題の一例です。
- 倉庫での棚卸誤差や在庫ロスが多い
- 紙の書類の記入に手間がかかっている
- 突発的なトラブルでラインが止まってしまうことが多い
- ○○さんしか担当できない作業がある
- 品質検査にばらつきがありクレームが発生している など
ビジョンと目標の設定
課題の特定後は、どのような姿に改善したいのか(DX導入後のビジョン)を明確にしたあと、具体的な数値目標も用意します。
例えば、「1年以内に棚卸し誤差率を5%から1%にまで引き下げる」「半年後までにクレーム件数を25%削減する」など、時期と数値が明確な目標を立てると進捗を確認しやすくなり、導入が頓挫するリスクを下げられます。
DX戦略の策定
目標を設定した次は、どのように改善を進めるべきか、DX戦略を立てます。これからどのように活動していくべきなのか、その方針を決定する過程です。
SWOT分析(自社の内外の環境についてプラス・マイナス要因を明確化する手法)を実行して現在のビジョンや目標が適切であるか確認したあと、初期・中期・長期の行動計画を用意しましょう。
ツール選定と導入計画の策定
DX戦略の策定後はツールの選定に移ります。目標の達成に必要な機能を持つツールや機材を選ぶ必要がありますが、少なくとも以下のポイントは押さえておくべきでしょう。
- 特定の機能の有無(例:WMS:倉庫管理システム、不良品検知)
- 自社と同業種の導入実績の有無
- 必要とされるIT知識のレベル(例:特定のプログラミング言語が必須)
- 初期費用とランニングコスト
特に費用は、製造業DXの取り組みを中断させないためにも重要です。無理のない時期や予算を想定した導入計画を立てましょう。
スモールスタートと効果検証
会社規模にもよりますが、製造業DXの場合、すべてのラインや工場を同時に改革するのは現実的ではありません。
まずは一部のラインにツールを試験導入し、期待する効果が得られる見込みがあるか確認しましょう。確認できた効果を社内で共有すれば、DXの意義が従業員に広く浸透します。
全社展開と運用体制の構築
スモールスタートから成果を得られたら、全社的な展開に進みます。ツールや機材のさらなる導入を進めるのはもちろん、社内の研修体制なども整えていきましょう。
部門間の連携がうまく進まない場合は外部のパートナーも取り入れた導入推進チームを立ち上げるのも有効です。
定期評価と改善
データを活用する製造業DXでは、導入後に得られたデータを分析し、その結果をもとにさらに改善策を検討して......と、PDCAサイクルを回すことで取り組みの質を高められます。
半年に一度、3ヵ月に一度など、定期的な効果測定と改善を欠かさないようにしましょう。
製造業DXを推進する際の最大の課題
製造業DXの導入が進まない場合の理由はさまざまです。特に実務においては、次の2つの理由が最大の課題として立ち塞がる傾向にあります。
製造業DXの構想が立てられない
1つ目の理由は、製造業DXの構想を立てられないことです。ひと口に製造業DXといってもその施策は幅広く、自社に適した構想を立案する必要があります。まずは何から手をつけるべきかを判断する力が求められます。
DXを推進する人材がいない
2つ目の理由は、製造業DXを推進できる人材が社内にいないことです。経営層に構想があっても、それを形にできる社員が不足しているために導入が進まないケースも多くあります。
この2つを解決するためには、外部サービスの力を用いる方法もあります。パーソルクロステクノロジーでは、製造業DXの構想作成の支援やその後の戦略コンサルティングで、製造業DXに取り組む企業を支援しています。
サービス:製造DX構想策定支援
サービス:DX戦略コンサルティング
製造業DXの導入事例
最後に、パーソルクロステクノロジーによる製造業DXの導入支援事例をご紹介します。
ある製造業者では、専門的な知識を持つ社員の不足に加え、「製造業DXにどこから着手すべきかわからない」という課題を解決するため、パーソルクロステクノロジーの製造DX構想策定支援サービスを導入しました。
この事例では、パーソルクロステクノロジーのトップがプロジェクトリーダーとなり現状の把握を実施。部門間で途切れていた業務フローやシステムを整理し、理想的なDXプランを提案しました。3年での目標数値達成を目指し、計画を実行に移していくフェーズに入っています。
製造業DX導入に課題があるときは支援サービスを活用しよう
製造業DXとは、デジタル技術によって自社のビジネスモデルさえ変えてしまうほど、製造に関する効率化をあらゆる側面から進めていく取り組みです。
製造業DXをスピーディーに進めるためには、製造業とITの知見を併せ持った高度な人材が欠かせません。しかし、そうした人材の確保や育成には少なからずコストや時間を要します。製造業DXに関してお困りの際は、パーソルクロステクノロジーの支援サービスをぜひご活用ください。
サービス:製造DX構想策定支援
サービス:DX戦略コンサルティング