EOLとは?放置によるリスクと対策、EOSとの違いも解説
ハードウェアやソフトウェアには、EOLと呼ばれる寿命があります。EOLの概要は理解していても、EOSなどの関連用語との違いやEOLに対応しないことでのリスクがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、EOLの意味から対応方法まで、EOL対応の基本となる情報をわかりやすく解説します。
>【無料お役立ち資料】EOLの課題と解決事例
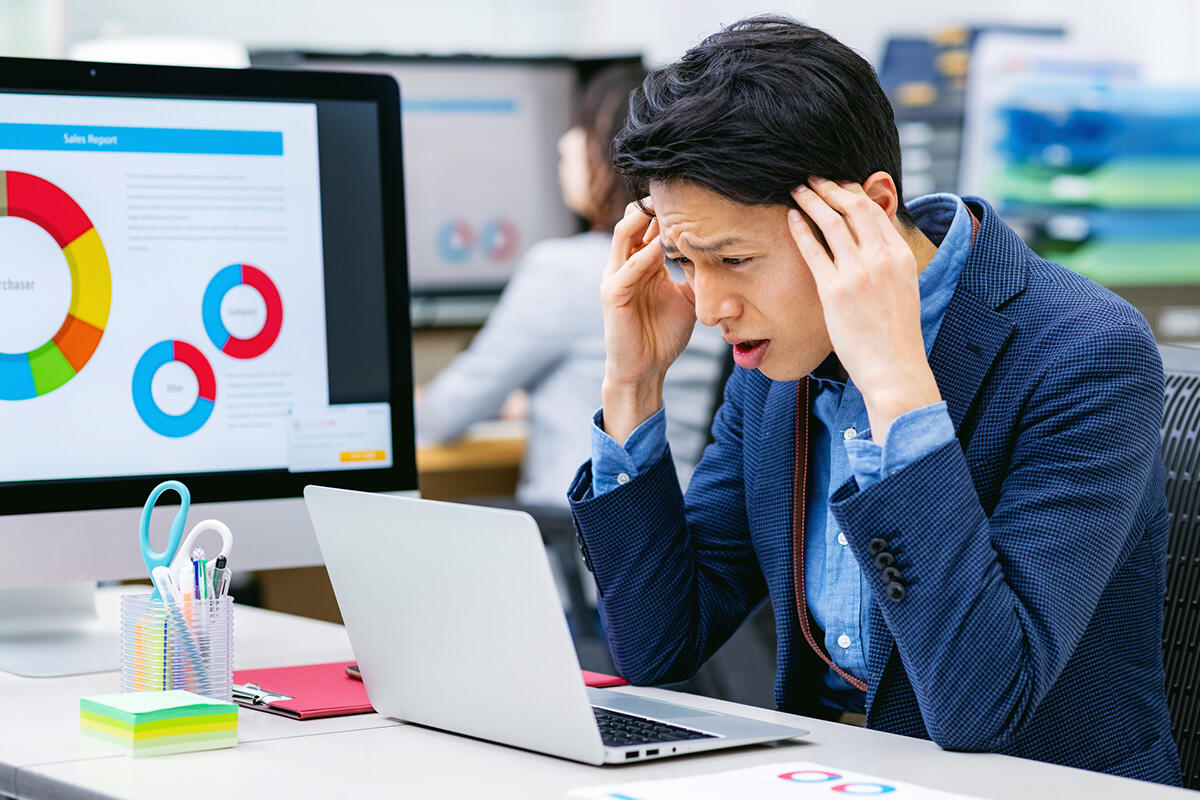
目次
パーソルクロステクノロジーのEOL対応支援サービスは、代替部品の調査・選定に留まらず、制御プログラムや筐体の変更など、ものづくり全般に関わる技術領域をワンストップで提供しています。
EOL対応で課題をお持ちのお客さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら
EOLとは?
まず、EOLという言葉の意味や関連用語との違いなどを解説します。
EOLの意味
EOLとはEnd of Lifeの略で、製品やサービスのライフサイクルが終わり、提供元であるメーカーからのサポートが終了することを指します。EOLを迎えたあとは、メーカーによる技術的なサポートやセキュリティアップデートなどが受けられなくなります。
EOSやEOSLとの違い
EOSはEnd of Salesの略で、製品やサービスの販売終了を、またEOSLはEnd of Service Lifeの略で、製品やサービスのサポートサービスの終了を意味します。
EOSは単に販売が終了するだけであり、購入済みの製品やサービスのサポートは引き続き受けられます。EOLとEOSLはどちらもサポート終了というほぼ同じ意味合いを持ちますが、EOSLはハードウェア単体のサポート終了日、EOLはハードウェアとソフトウェア両方のサポート終了日を指す場合があります。
ただし、メーカーによって厳密に使い分けている場合もあるため、使用している製品のメーカー情報を確認してみましょう。
EOL担当者(情シス担当者・製造担当者)のよくあるお悩み
EOLを迎えると製品やサービスのさまざまなサポートが受けられなくなるため、製品やサービスの置き換えを検討する必要があります。しかし「妥当な代替品を見極められない」「明確な担当者が決まっておらず責任の所在がわからない」などの理由でEOL対応が進まないこともあります。
製造業などで利用する設備機器においては、完成形の製品と製品の中の部品それぞれにEOLがあります。製品であれば高額な製品の置き換えが必要となり、部品であれば置き換えた際の周辺機器との互換性を十分にチェックする必要があります。そうした点もEOL対応のハードルが上がる要因の1つです。
一方、セキュリティリスク対策のために情シス担当者が現場に対してEOL対応を急かすというシーンが多く発生しています。
ではなぜ、メーカーはこれらの原因となるEOLを設定しているのでしょうか。次章では、メーカーがEOLを設定する理由、またどのようにこれらのハードルを乗り越えていくべきなのかをまとめていきます。
EOLをメーカーが設定する3つの理由
メーカーがEOLを設定する主な理由を3つご紹介します。

技術は常に進化しているから
近年は技術革新のスピードが速まっており、市場のニーズに対応するためには新しい機能の取り込みやさらなる性能向上を図る必要があります。
しかし、最新技術やセキュリティ要件に対応する際、単純なアップデートでは対応できず、製品やサービス全体での変更が必要になるケースも多々あります。そのため、一定期間でEOLを設定して技術革新に適応していくことが一般的な取り組みとなっています。
新製品・新部品への投資に集中するため
EOLによって製品やサービスのライフサイクルを区切る背景には、リソース面の理由もあります。古い製品やサービスのサポートを維持し続けると、新しい製品やサービスを出すたびにサポート対象が増えてしまいます。限られたリソースのなかでより競争力のある製品やサービスの開発や改善に集中するため、多くのメーカーが一定期間で古い製品やサービスのサポートを終了しています。
古い製品・部品の維持コストを抑えるため
維持コストの観点でもEOLが設定される理由があります。製品やサービスをサポートするためには、修理部品の確保やデータ保持が必要になります。修理部品の確保には在庫管理コストがかかりますし、データ保持にはサーバーストレージのコストがかかります。適切なタイミングで維持コストを削減し、全体コストの最適化を図るという観点も、EOLが設定される理由の1つです。
EOL製品の放置で想定されるリスク
EOLによるトラブルは、企業にとって大きな損失をもたらすリスクがあります。EOL対応は情シスと現場担当者が連携して取り組む課題であり、お互いがそれぞれのリスク視点を理解することが重要です。
情シス担当者
情シス担当者にとっては、EOLがもたらすセキュリティリスクや、EOL製品が業務効率化の妨げとなる点が大きな懸念となります。
セキュリティが脆弱化する
EOLを迎えるとメーカーからセキュリティアップデートが提供されなくなるため、脆弱性が見つかっても対策できなくなります。また古い機器の場合、機能面の制約で社内標準のセキュリティソフトを導入できないケースがあります。結果としてセキュリティが脆弱な機器が残り、これらの機器のマルウェア感染や不正アクセスといったリスクへの対策が必要となります。
業務効率の低下につながる
情シスとしては、IT技術を活用して業務効率化を図りたい一方、古い製品やサービスが効率化に必要なシステムと連携できないケースがあります。それどころか、個別の製品やサービスに対応するためのコストが発生し、業務効率が低下する問題にもつながります。
製造担当者
製造担当者の視点としては、設備トラブルによる生産停止や、それに伴う信頼の失墜が深刻なリスクとなります。
トラブル時に対応してもらえない
EOL後は、故障や不具合が発生しても問い合わせ窓口やサポートサービスが停止されているため、トラブルに対応してもらえません。設備・システムの停止によって製造ラインや業務が止まるリスクがあり、状況によっては企業に多額の損失を引き起こすリスクが生じます。
顧客や取引先からの信頼が下がる
EOL製品を使い続けていると、顧客や取引先からリスク管理が不十分な企業だととらえられる恐れがあります。また、万が一セキュリティインシデントが発生し、生産停止や情報漏えいにつながれば、取引先や世間からの信頼を失うことになりかねません。
企業が取るべきEOL対策
EOL製品の放置によるリスクを避けるためには、企業としての計画的な対策が欠かせません。ここでは、EOLに備えるために企業が取るべき具体的な対応を5つご紹介します。
使用製品のEOLを確認する
まずは自社で使用している各製品のEOLを確認し、ライフサイクルのどの段階にあるかを把握しましょう。製造業などでは、設備部品のEOLも考慮する必要があります。各製品のEOLを把握し、いつまで使用可能かを明確にできれば、対応の優先順位も見えてきます。
事前にリプレイス計画を策定する
EOLまでの残り期間や重要度などを目安に優先順位をつけ、リプレイス計画を策定しましょう。導入スケジュールや予算などに余裕のある計画を作成することが大切です。導入時期やコスト、影響範囲などを整理し、事前に社内調整を進めておくことで、スムーズに置き換えができます。
後継機種・代替製品を調査する
リプレイス計画に沿って、後継となる製品や代替手段の情報収集をおこないましょう。既存環境との互換性や性能、導入コストだけでなく、サポート体制まで含めて比較検討することで、より現場に適した選択ができます。
第三者保守の活用も検討する
EOLまでにリプレイスが難しい場合には、第三者保守サービスの利用も検討しましょう。第三者保守とは、メーカーの公式サポートが終了したあとも専門業者が保守や修理を代行してくれるサービスです。
ただし、これはあくまで暫定的な対応策です。第三者保守を利用する場合でも、できるだけ早めにリプレイスを進める必要があります。
EOL支援サービスを検討する
ここまでEOL対応の進め方を解説しましたが、やるべきことはわかっているが現場のリソースが足りていない、具体的にどうやって互換性や性能を検討すべきかわからない、というケースも多いのではないでしょうか。特に設備機器においては、電子部品など細かなEOLも管理していく必要があるため、EOL対応のハードルが高くなりがちです。
EOL対応に課題がある場合は、EOL支援サービスの活用も検討するとよいでしょう。パーソルクロステクノロジーのEOL対応支援サービスでは、該当機器や部品の調査から、代替部品の選定や置き換え、置き換え後の評価までをワンストップでご提供しています。EOL対応で課題をお持ちのお客さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
サービス:EOL対応支援サービス
製造業でのEOL対策事例
ビジネス環境の変化が速まっている現代では、設備や部品メーカーの再編や生産合理化などの動きもあり、EOL対応がより難しくなっています。
製造業のある企業では、EOL対応が必要な設備や部品が急増し、本来は新規製品の開発に充てたいリソースをEOL対応に割かなければならない状況でした。
そこで、EOLの調査からリプレイス、評価までをワンストップで依頼できるEOL対応支援サービスを導入。スムーズなリプレイスが実現したことに加え、1部品あたりの対応コスト削減などにもつながっています。
事例:EOLサービスのご提案
EOL対策に課題があるなら専門サービスを活用しよう
EOLは製品やサービス、または関連する部品などのサポート終了を指し、EOLとなった場合はメーカーサポートを受けられなくなります。EOL対策を怠ると、故障やセキュリティのリスクが増大し、生産停止や業務停止などの深刻な問題につながる恐れがあります。
リスクを避けるためには、使用中の製品や部品におけるEOL状況を把握し、計画的なリプレイスを進めることが重要です。一方で、自社のリソースでEOLまでのリプレイスが難しい場合は、第三者保守や支援サービスの活用を検討する必要があります。
パーソルクロステクノロジーでは、医療機器や車載部品をはじめとした、ざまざまな部品のEOLに関する事前調査や代替品の検討、リプレイス、評価までをワンストップでご支援しています。製品部品のEOL対応に課題感をお持ちの際はぜひお気軽にお問い合わせください。
サービス:EOL対応支援サービス


