PLM(製品ライフサイクル管理)とは?製造業での導入メリットと選び方
ニーズの多様化や技術の進歩などにより企業を取り巻く環境が急速に変化する現代の製造業では、製品のライフサイクルを効率的に管理することがますます重要になっています。そこで注目されているのが、PLM(製品ライフサイクル管理)という手法です。
この記事では、PLMの基本から導入の利点、選定時のポイントまで、わかりやすく解説します。
>事例:わずか3ヵ月、短期間のPLM導入でデータ探索時間を激減。

目次
パーソルクロステクノロジーでは、豊富なノウハウと技術でお客さまに最適なPLM導入を支援しています。
PLM導入による製品開発力、企業競争力強化にご興味をお持ちのお客さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら
製造業で重要となっているPLM(製品ライフサイクル管理)とは?
PLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)とは、製品の企画から設計、開発、販売、廃棄といった製品のライフサイクルを統合的に管理するシステムを指します。PLMによって各プロセスの技術情報がエンジニアリングチェーンとして結びつくことで、製品開発力や企業競争力の強化につながります。
PLMの導入が進んでいる背景
PLMの考え方は1990年代に登場したとされており、2000年代に入って導入が本格化しました。背景には、グローバル化やIT技術の発達により製造業が扱うデータの量と種類が増加し、それらを効率よく管理する必要性が高まったことが挙げられます。特に自動車産業や電機産業などでは製品開発のスピードや多様化への対応が求められ、PLMの活用が進んでいます。
PDMやMESとの違い
PLMと類似するものとして、PDM(Product Data Management:製品情報管理システム)やMES(Manufacturing Execution System:製造実行システム)といったシステムがありますが、それぞれ目的と管理範囲が異なります。
PDMは主に製品設計に関するデータを一元管理するシステムで、PLMに比べて対象範囲が限定的です。一方、MESは製造現場への指示や製造実績の収集・管理、トレーサビリティなど、製造の実行にフォーカスしたシステムです。PLMが設計(製品設計だけでなく、設備設計や工程設計も含む)データを扱うのと比較すると、MESは実績のデータを扱うという違いもあります。
PLMの代表的な機能
製品ライフサイクル全体を管理するPLMには、各工程に応じたさまざまな機能があります。ここではその代表的な機能をご紹介します。
【企画段階】プロセス設計・要件定義
企画段階としては、ポートフォリオ管理や要件管理、プロジェクト管理機能があります。ポートフォリオ管理によって既存製品のポートフォリオをふかん俯瞰して収益の高い製品を生み出すためのリソースを効率的に管理することや、市場ニーズを満たす要件を明確に管理することができます。
昨今のソフトウェア開発の比重が高い製品開発においてMBSE(Model Based System Engineering)への対応は必須になっています。MBSEを実現するためR(Require:要求)、F(Function:機能)、L(Logic:論理)、P(Physical/Product:物理)の管理や1D/3DCAEとの連携も最近のPLMでは可能になっています。
また、ポートフォリオ管理や要件管理をもとに企画立案した製品に対して、プロジェクト管理機能によるマイルストーンの設定やガントチャートを使うことで、無理のない開発計画を作成できます。
【設計段階】CAD連携・BOM最適化
設計段階では、製品設計機能やCADデータ管理機能があります。PLMでは、複数のCADソフトウェアから設計情報を取り込み、一元的に管理できます。
設計段階では仕様書、図面、3Dデータ、その他各種ドキュメントが必要となり、従来ではその情報を探すのに苦労していました。PLMではBOM(Bill of Materials:部品表)にこれらの情報が紐づいており、簡単に欲しい情報にアクセスすることが可能です。
また、PLMはBOMにも対応しており、設計BOMや製造BOM、保守BOMなど、製品ライフサイクル全体のBOM情報を集約できます。
【生産準備段階】BOP構築
最近のPLMではBOP(Bill of Process:製造工程表)の導入も進んでいます。従来は工程設計、設備設計、QC(品質管理)などの情報は人の頭、紙、Excelの中にしかありませんでした。これらの情報をPLMシステムの中のBOPというデータ体系に格納することにより、工程設計データを一元管理することが可能となり、これらの情報から各種生産指示の帳票を自動的に作成することができます。
設計データと連携しているため、設計のどこが変化し、工程情報にどう影響するのかを迅速に把握し、設計の変更点をBOPや帳票に自動反映することも可能です。
【製造段階】ERP連携・製造BOM展開
製造段階においては、PLMの製造BOMやBOPをERP(基幹業務システム)やMES(製造実行システム)と連携することが可能です。プロジェクト管理機能によってタスクの管理や納期に関わるスケジュール管理も行えます。
【下流段階】運用・定着・保守支援
下流段階では、製品の品質を管理する機能、不具合や顧客のクレームを記録・分析する機能などが活用できます。下流段階の情報を適切に収集し管理することで、より顧客ニーズを満たす新製品の開発につなげられます。
製造業でPLMを導入するメリット
製造業でPLMを導入すると、さまざまなメリットが得られます。代表的なメリットをご紹介します。
業務効率の改善
PLMがあれば、製品に関わる情報を1つのシステム上で統合管理できるようになります。情報が集約されることで、設計、製造、販売、保守といった各工程の連携が円滑になり、工程全体の生産性向上につながります。各部門の業務効率化の方法やナレッジも共有しやすくなるでしょう。さまざまな情報を探索する時間を大幅に削減することが可能になります。
製品の品質改善
PLMを活用すれば、設計の早い段階で、さまざまな部署が情報を共有し、設計情報の問題点、加工のしやすさ、組み立てのしやすさ、品質が確保しやすい製品設計を実現するためのフィードバックが可能となります。それにより品質が向上するのはもちろん、手戻りも少なくなり、リードタイムの短縮やコスト削減につながります。
ライフサイクルコストの最適化
PLMを導入すると過去に使用した部品、工程、現有設備の情報が簡単に探索できます。過去に使用した部品を流用することで設計、製造コストを削減し、品質も確保しやすくなります。
設計段階で既存の設備や治工具の情報を参照し、それらを活用できるように設計することで、新たな設備や治工具の設計・製作を最小限に抑えることができ、固定費の大幅な削減が可能になります。併せて、品質の向上にもつながります。
顧客満足度の向上
市場やユーザーから得られた情報をいち早く製品設計に反映させることで、顧客の期待に応える製品をすばやく提供できます。顧客ニーズを満たす製品をタイムリーに提供し続ければ顧客満足度が向上し、リピート率アップやブランディングの強化につながるでしょう。
PLMシステムの選び方
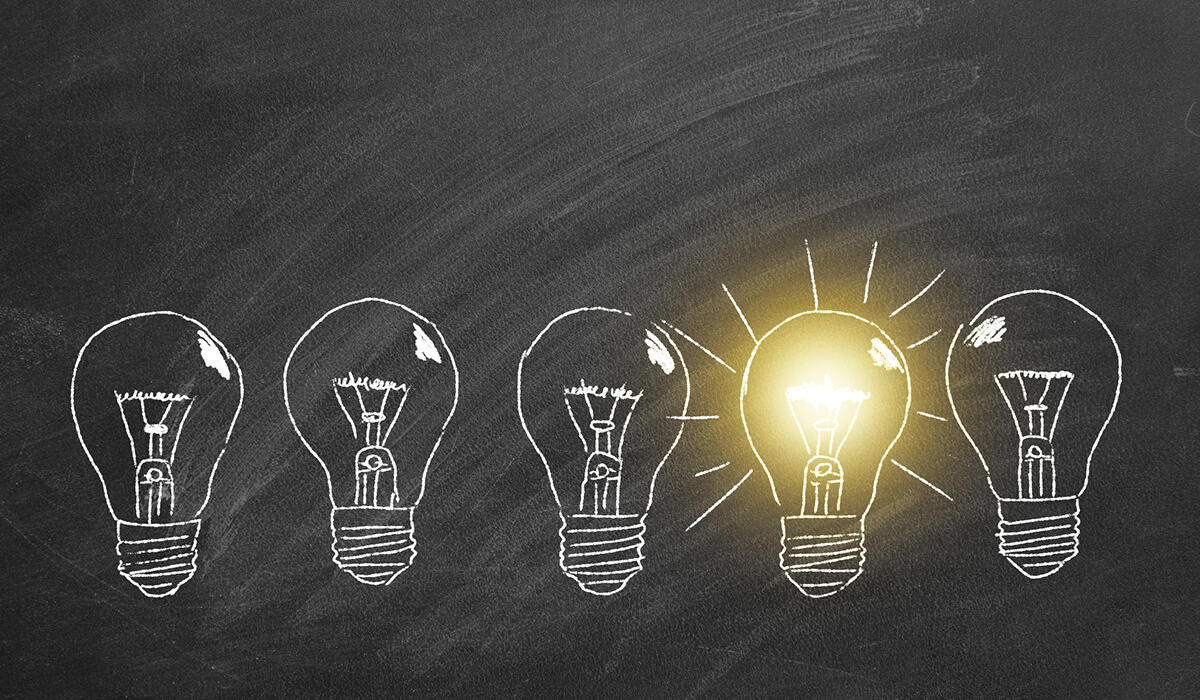
PLMを導入する際は、自社の目的に合ったものを選ぶことが重要です。自社に合わないシステムを選ぶと、運用が定着しなかったり、想定した効果が得られなかったりする恐れがあります。ここでは、PLM選定の際に確認すべきポイントをご紹介します。
業務課題は何か
まずは自社の業務課題を把握し、PLMの導入によってどの課題を解決するかを明確にしましょう。「設計情報が属人化していて情報共有が難しい」「図面や部品表の変更管理が煩雑」などといった具体的な問題を洗い出すことで、どのような機能が必要なのかが見えてきます。現場で発生している課題を洗い出し整理することがPLM活用の出発点です。
業務プロセスに適合するか
既存の業務プロセスを大幅に変更すると生産効率が落ち、収益の低下につながる恐れがあります。PLMを選ぶ際は、無理に業務をシステムに合わせるのではなく、業務に合うシステムを選ぶようにしましょう。PLMの標準的な機能はどの製品にも搭載されている場合が多いですが、細かい仕様は製品によって異なります。自社の業務に合う仕様かどうかをPoC(仮想実証)で確認しましょう。
既存システムとの連携性が高いか
PLMは、ERPやMESなど他システムと連携することでより大きな効果を発揮します。既存システムと連携できない場合、PLM導入の効果を十分に得られないため、既存システムと連携しやすい製品かをチェックしましょう。ベンダーの導入実績を事前に確認しておけばトラブルも起きにくく、安定した運用が期待できます。
将来の業務変化に対応できるか
市場変化や技術進化のスピードが速まっている現代では、5年後、10年後の業務変化を見据えて製品を選定することも重要になっています。将来的な製造ラインの縮小・拡大や海外への生産拠点展開などを想定し、PLMの拡張性やクラウド移行の可否を確認しておきましょう。
導入・運用サポートは十分か
PLMを導入しても、現場に定着しなければ効果は得られません。構築や導入のみでなく、導入後のトレーニングや定着支援など、伴走的な支援を提供してくれるベンダーの製品を選ぶと安心です。運用開始後のトラブル対応のしやすさやリスク対策にもつながります。
総合的なコスト評価はどうか
PLMは複数の工程に係る大きなシステムです。長期的な運用が見込まれるため、導入費用だけでなく、保守や運用にかかる総合的なコストも評価する必要があります。TCO(総保有コスト)の観点でこれまでご紹介したポイントと照らし合わせ、長期的に費用対効果が高いかを判断しましょう。
カスタマイズ性
PLMは、ERP(基幹業務システム)とは異なり、主に知的作業を支援するためのシステムです。
そのため、使いやすさや創造的な業務への対応力が非常に重要なポイントとなります。この特性から、PLMは企業ごとの業務に合わせて多くのカスタマイズが行われることが一般的です。
しかし、カスタマイズには導入期間やコストの増加だけでなく、PLMシステムのバージョンアップ時にさらなる検証作業や追加コストが発生するという課題があります。その結果、PLM自体が進化しても、カスタマイズの影響で新しい機能を活用できないケースが多く見られます。
こうしたリスクを避けるためには、コードを書かずに設定ができるほか、ローコードで柔軟にカスタマイズが可能なシステム、さらにバージョンアップにもスムーズに追従できるPLMを選定することが望ましいと言えるでしょう。
PLMの導入で注意すべきこと
続いて、PLMの導入時に注意すべきポイントを解説します。
スモールスタート
PLMはスモールスタートで導入・展開を進めましょう。特定の部門で限られた機能に絞ってPoCを行い、実際の効果を確認しながら、段階的に機能や対象範囲を広げていく方法が現実的です。いきなり複数部門に導入を進めると、あとから調整が利きにくくなり、結果として現場に定着しない恐れがあります。
既存システムとの連携
既存システムとの連携性は重点的にチェックしましょう。PLMは単体で完結する仕組みではなく、ERPやMESなどライフサイクル全体に関係する他システムと連動させることで大きな効果を発揮します。特に独自のシステムを開発して利用している場合には、そのシステムと連携可能かを確認しておきましょう。
専門人材の確保
PLM導入後の継続的な運用と改善のためには、専門知識を持った人材が必要です。しかし、PLMの運用には製造とIT両面の知識やスキルが必要となります。自社のリソースだけで対応するのが難しいケースもあるため、適宜外部の専門家やパートナー企業の活用も検討しましょう。
PLMの導入事例【エンジニアリングプロセスの効率化】
ある企業では、設計開発や生産で使用するCAD・帳票のデータが管理できておらず分散されており、その課題の解決策としてPLMを導入。同時に導入支援サービスも利用したことでPLMの構築やデータ移行はスムーズに進みました。
その結果、エンジニアリングプロセスにおける情報収集の効率が大幅に上昇。結果として、わずか3カ月という短期間でPLMの導入が完了し、多くの工程で工数削減を実現しています。
事例:わずか3ヵ月、短期間のPLM導入でデータ探索時間を激減。
PLMで製品開発力や企業競争力を強化しよう
PLMは、製品の企画から設計、製造、販売、保守、廃棄までの情報を一元管理し、各工程の業務効率化や部門間の連携強化を実現するシステムです。導入によって、業務効率化や品質向上、コスト最適化、顧客満足度の向上が期待できますが、自社の業務に合ったシステムの選定と段階的な導入が必要となります。
今後はAIの活用が不可欠となるため、データが適切に管理されていなければ、AIによる業務効率化は実現できません。AIを効果的に活用するためには、まずPLMの導入とデータの一元化を早急に進めることが求められます。これを怠ると、競争力の維持が難しくなるでしょう。
また、PLMの導入に加えて、運用や保守の観点からクラウド化を検討し、さらにPLMの先にあるデジタルツイン化も視野に入れる必要があります。
これらのことから、トラブルなく導入を進め最大限の成果を獲得するためには、導入支援サービスの活用を検討するのがおすすめです。パーソルクロステクノロジーでは、豊富なノウハウと技術でお客さまに最適なPLM導入を支援しています。PLM導入だけでなく、AI活用、クラウド化、デジタルツイン化などPLMの向こう側のグランドデザインも可能です。
PLM導入による製品開発力、企業競争力強化にご興味をお持ちの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
サービス:PLM導入支援


